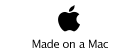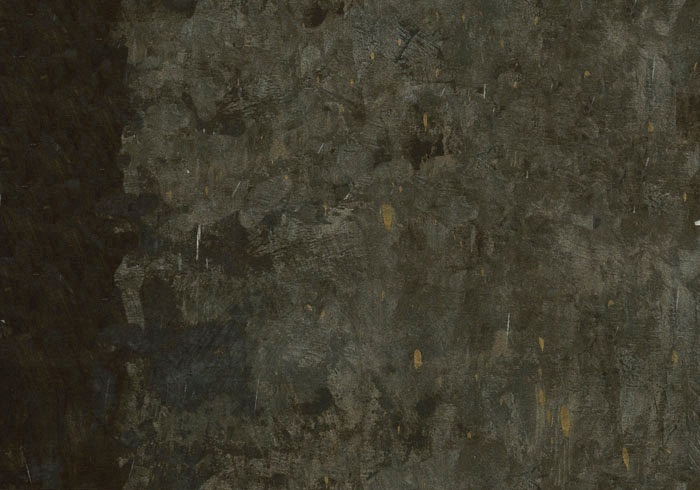
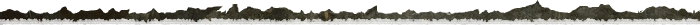
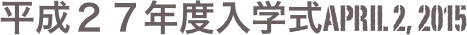
平成27年度入学式 総長告辞
歴史的大変革期を生きる
大阪大学に入学ならびに進学されました皆さん、おめでとうございます。また、ご臨席いただきましたご家族の皆さま、関係者の方々に心よりお祝い申し上げます。
あらゆる可能性を秘めた前途洋々たる皆さんは、本日、大阪大学の一員として、あらたな人生を踏み出すその第一歩を迎えられました。大阪大学総長としてこの上もない喜びであり、大阪大学は心から皆さんを歓迎いたします。
適塾から大阪大学へ、そして世界適塾へ
はじめに、皆さんがこれから過ごす大阪大学について、少しお話をいたします。大阪大学は、1931年に我が国第6番目の帝国大学として設立された大学ですが、創立の準備金や当座の運営資金を大阪の有志が出資して開設されたという歴史的経緯を持つ大学です。その大阪大学の原点は、江戸時代末期の1838年に緒方洪庵が設立した「適塾」に見いだせます。外国語学部の前身である大阪外国語学校出身の、すなわち皆さんの大先輩である司馬遼太郎が小説『花神』の冒頭で、適塾を大阪大学の「前身」、緒方洪庵を「校祖」と表現しています。
適塾には全国から1000名以上の塾生が集まり、日夜勉学に励みました。その中には塾頭を務め、後に慶応義塾大学を創設した福沢諭吉、彼の後に塾頭を務め、我が国の医療制度、公衆衛生制度の基礎を築いた長与専斎(ながよせんさい)、安政の大獄で25歳の若い命を落とした橋本左内、日本赤十字社の前身の博愛社(はくあいしゃ)を創設した佐野常民(さのつねたみ)、明治政府で近代的な軍隊制度を創った大村益次郎(ますじろう)、外交で列強各国と対峙し活躍した大鳥圭介、さらには1810年に設立された東京大学医学部の初代綜理を努めた池田謙斎(けんさい)など、様々な分野でリーダーとして活躍した人々が適塾で育ちました。大阪大学医学専門部の卒業生で、ブラックジャック、鉄腕アトムなどで有名な漫画家の手塚治虫が自らのルーツを描いた「陽だまりの樹」という作品があります。このなかで描かれている手塚良庵(てづかりょうあん)は手塚治虫の曾祖父で、緒方洪庵の弟子として福沢諭吉らとともに学んだ蘭方医です。彼らは「人のため、世のため、道のため」という緒方洪庵の精神にもとづき、明治初期における我が国の近代化に大きな役割を果たしたのです。適塾は、医学を伝習する場所として開設されましたが、医者を目指していた者だけが集まったのではありません。長与専斎は「元来(がんらい)適塾は医科の塾とはいへ、其実(そのじつ)蘭書解読(らんしょかいどく)の研究所にて、諸生には医師に限らず、兵学家もあり、砲術家もあり、本草家(ほんぞうか)も舎密家(せいみか)も凡そ(およそ)当時蘭学を志す程の人は皆この塾に入りて、其(その)支度をなす・・・」と回顧しています。このように、舎密(せいみ)すなわちケミカルの分野など、蘭学を介して様々な西洋の学問にも塾生は興味を持っていました。
このように適塾の自由闊達(じゆうかったつ)な学問的気風と先見性の下(もと)で学んだ若い有志が、明治維新という我が国の新しい時代を切り開く大きな原動力になり、その適塾の精神は1869年に設立された大阪仮病院に継承され、大阪医学校や大阪府立医科大学を経て、1931年に医学部と理学部の2学部からなる我が国6番目の帝国大学となる大阪帝国大学へと繋がります。その後1933年には、1896年に設立された大阪工業学校が工学部として加わりました。戦後、新たに法文学部が加わった際に、江戸時代後期、大坂町人が町人のために漢学と国学などを伝習した「懐徳堂」の蔵書類が、懐徳堂文庫として本学に寄贈され、大坂の町に息づいた独創的な学問と思想・文化を受け継ぐに至りました。
1949年に新制国立大阪大学として再スタートした際には、法文学部を文学部と法経学部に改組し、現在の総合大学としての骨格が整いました。その後、法経学部は、法学部と経済学部に改組され、歯学部、薬学部、基礎工学部や人間科学部などを新設し、2004年の国立大学法人化を経て、2007年には、1921年に設立された大阪外国語大学との統合により、現在、11学部、16研究科、5附置研究所を擁(よう)する我が国屈指の研究型総合大学に成長しました。1931年の本学開学当時、医学部と理学部あわせて86名だった新入生数は、80年を経て、学部学生の定員では国立大学の第一位の規模となり、学部学生と大学院学生合わせて6400名に及ぶ皆さんが毎年入学されるまでに発展しました。また大阪大学の現役の学生さんは様々な分野で大活躍しています。例えば、昨年は文学研究科哲学の修士2年生の糸谷哲郎さんがプロ将棋の最高峰である竜王を獲得しました。また現役の学生さんが世界で13人目、女性としては世界初のレゴマスターを獲得、学生落語日本一や全国学生環境活動コンテスト2年連続グランプリを獲得するなど大活躍しています。さらにエコノミスト誌が昨年発表した企業の人事部の評価ランキングで阪大生は日本1位に輝きました。
このように、177年前に設立された「適塾」を原点として、「懐徳堂」の精神を受け継ぎ、大阪府民の熱意に支えられた本学は、「地域に生き世界に伸びる」をモットーに、我が国を代表する国立総合大学として、世界に向かってたゆみなく発展を遂げるとともに、数多くの優れた研究者、教育者、文化人、そして政財界など各界の指導者や卓越した人材を世に輩出してきました。今から16年後の2031年には大阪大学は創立100周年を迎えます。その時、大阪大学は、「世界適塾」として世界でトップ10に入る研究型総合大学になることを目指しています。適塾には日本各地から志ある若者が集まり、適塾で学んだ新しい知識や技量を携え、再び全国に散らばり明治維新の新しい時代を切り開きました。「世界適塾」には、世界中から向学心溢れる人たちが大阪大学の学問と研究を目指して集まり、学問や研究を究め、やがて大阪大学から世界中に羽ばたいていきます。「世界適塾」の理念は「学問による調和ある多様性の創造」により心豊かな人類社会の発展に貢献することです。
私たちは歴史的大変革期に生きている
20万年位前にアフリカを起源としてホモ・サピエンスが誕生して以来、人類は数万年の歳月をかけてユーラシア、オーストラリア、アメリカ大陸へと移動、拡散して行きました。そして、1万年から数千年前にメソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、中国文明、マヤ文明等の様々な文明が各地に開花しました。その過程で様々な宗教が生まれるとともに、言語や文化などの多様性が生まれて来ました。これらの様々な多様性を有する人類は長い歴史のなかでお互いが影響し合い、かつ対立を引き起こし、時には戦争すら引き起こして来ました。また多様性が交わる事で人類社会に様々な革新的な変革がもたらされました。さらに多様性は人類社会に心の豊かさをもたらしました。このように人類の長い歴史は多様性がもたらす発展と多様性ゆえに生じる対立や戦争の歴史であったと言う事ができると思います。そして今、20世紀に花開いた科学・技術の急激な発展により人類は大きなグローバル化の波に飲み込まれています。例えば飛行機の普及によってわずか半日で大陸を横断する事ができます。またインターネットにより瞬時に情報が世界中に伝わるようになりました。移動手段や情報伝達手段の発展に加えて、急激に進む人口の増加があります。現在70億人、そして2050年には90億人を超えると推定されています。このように、移動手段や情報伝達手段のみならず、人口増加の観点からも地球は飛躍的に狭くなりつつあります。長らく比較的広大な地球に存在していた多様性は今狭い時間空間に凝縮されようとしています。多様性の凝縮により21世紀は多様性の爆発の世紀になる可能性すらあります。加えて急激な人口の増加や技術革新は食料問題、エネルギーや環境問題、さらには感染症問題や生物多様性の危機など、様々な要因が複雑に絡んだ地球規模の深刻な問題を投げかけています。このように、今、人類はかつて経験したことがない、地球規模の歴史的大変革期に直面しています。皆さんは、我々大学人はこのような地球規模の様々な問題を解決していく道を探求して行かなければなりません。これは21世紀のグローバル社会に生きている皆様や我々大学人の責務です。
さらに21世紀の大学に求められているもう1つの大きな責務があると思います。それは「学問による調和ある多様性の創造」です。グローバル社会では、言語・人・文化・宗教・政治などの多様性が存在します。これらの多様性は人類社会の発展の原動力であるとともに、人類社会を豊かにしてきました。その一方、時として様々な障壁となり紛争や戦争すら引き起こす基になります。大学には人類に普遍的な共通言語である「学問」が存在します。学問は芸術、スポーツや経済活動などと並んで、人類共通の言語であり、多様性がもたらす様々な障壁を乗り越える大きな力を有しています。学問をすることにより、皆さんは言語や文化や宗教を異にする世界中の様々な人々と友達になり、人の輪を世界中に際限なく広げることができます。そして、多様な背景を持つ世界中の人と学問を介して得られた永遠に続く「絆」は、経験と人的交流を持って拡散し、世界中に「調和のある多様性」をもたらすことが可能です。これこそが、21世紀の大学の大きな役割です。
糟粕を嘗る勿れ
初代総長で、我が国における原子物理学の父であり、土星型の原子模型を提唱した長岡半太郎先生は次のような言葉を残しております。
「糟粕(そうはく)を嘗(なむ)る勿(なか)れ」
長岡総長はこの言葉を直筆の額として本学に残しており、現在、それは総長室に掲げられています。糟粕とは酒の搾りかすで、滋養すなわちスピリッツをとりきった不要物、精神のない遺物(いぶつ)などを意味します。「糟粕を嘗る勿れ」とは、すなわち「先人の精神を汲み取らず、形だけをまねるようなことはするな」という意味です。この精神のもとに、湯川秀樹先生は大阪大学理学部で中間子理論を完成されました。この研究により先生は大阪大学理学博士の学位を取得されるとともに、日本人として初めてのノーベル賞を受賞されました。湯川先生の愛用の黒板は理学部にあり、学生さんらが自由に使用して意見交換会などに活発に使われています。
これこそが適塾から現在につながる大阪大学で、皆さんに体得して欲しいと願う学問の姿勢です。大阪大学は、皆さんが常に先進的で独創的な研究ができる環境を提供します。しかし、その機会は皆さん自らが求めなければなりません。常に独創的であるためには、「物事の本質を見極める」姿勢が必要になります。漫然と過ごすだけでは見逃してしまう疑問、不条理、変化、そのようなものに皆さん自身が気づく感受性を養わなければなりません。たとえば、皆さんが大学で行う様々なクラブ活動、NPO法人活動への参加、夏期休暇を利用した海外研修など、大学のキャンパスや周辺にその機会は溢れています。大学院生の皆さんにとっては、実験やフィールド調査等を介して、より具体的に目の前の自然現象や社会現象に潜む物事の本質を追求する機会が溢れています。その機会を決して逃さないことです。その機会をものにできるか否かは皆さん一人一人の感性、好奇心、観察力、考察力、粘り強さと、そこから芽生える「ひらめき」にかかっています。今までのように先生が一つ一つ物事を教えてくれる訳ではありません。教員も真の答えを求めて日夜研究しているのが大学です。ただ机に座って授業を受けていればそれで物事の本質がわかる訳ではありません。また、物事の本質が皆さんのもとに向こうから微笑んで近づいてくる訳ではありません。それは、自ら求め、心の準備ができている人にのみ、ある日、ある時、突然訪れるのです。
胡蝶の夢
荘子の中に次のような一節があります。(「荘子」、岸田陽子訳、徳間文庫より)
昔(むかし)荘周(そうしゅう)夢に胡蝶(こちょう)となる。栩栩然(ききぜん)として胡蝶なり。自ら愉(たのし)みて志に適(かな)えるかな。周たるを知らざるなり。俄然(がぜん)として覚(さ)むればすなわちきょきょ然(ぜん)として周(しゅう)なり。知らず、周の夢に胡蝶となるか、胡蝶の夢に周となるかを。
夢の胡蝶が今の自分を夢見ているのか、それとも今の自分が夢で蝶になっているのか?さらに、荘子は、何が真実かという問いかけに対して、この世の中には絶対的に真実といえることはない。ものの見方を変えれば、例えば己(おのれ)を「これ」と呼び、他(た)を「かれ」と呼ぶ、しかし「かれ」からは己も「かれ」、「かれ」も「これ」である。このように物の見方は、立場をかえればなにが正しく、なにが誤りであるとは言い難(がた)い。
この荘子の考え方の中に、「物事の本質」というものを垣間見ることができます。皆さんがこれまで学んできた知識はすべて、ある一面からみた知識に過ぎません。荘子が言うように物事は見方を変えれば全く異なる姿が見えてきます。皆さんもこれからは様々な問題意識をもって、ある事柄を一面から見ることなく、様々な観点から見る、すなわち複眼的に見る努力をして欲しいと思います。そこに物事の本質を観ることができます。
歴史的大変革期を生きる
皆さんは、この大変革期を生きるにあたり、日本は勿論もっと広く世界に目を向け、「社会の変化に対応する」力を身につけなければなりません。では、現代の社会が求める人材、その能力とはどのようなものでしょうか?例えば、決断力、行動力、そして言語運用能力を含むコミュニケーション能力。これらは、しばしば優れたリーダーの素質として語られます。確かにこれらの能力を身につける必要はあります。しかし、急速に変化し続ける現代社会においては、これらの汎用的能力だけでは十分ではありません。これからの社会が求める人材とは、多元的な課題に潜む物事の本質を見極め、従来からの常識や考え方を超えた課題解決を先導できる人材であると私は考えます。「物事の本質を見極める力」とは、現象として認知可能な事象の奥に潜む、その事象のカギとなるもの、そしてその仕組みを見極める力を意味しています。「一芸に秀でた者は総ての道に通じる」という言葉があります。この力の基盤となるのは、特定の分野をとことんまで究めた高度な専門性です。大学が最先端の研究を行い、それに基づく高度な専門教育を行う意義はここにあるのです。
また、物事の見方の転換も重要かもしれません。例えば、科学技術の力で自然を征服するという発想ではなく、如何にすれば人類は自然と共生できるかを真剣に考える必要があります。また老・病・死など人間が避けて通れない問題も、今までは生命科学や医学の発展により克服するという姿勢で研究が行なわれてきました。しかしそのような発想を転換し、どのようにすれば人類はこれらの問題と共生し心安らかな人生を全(まっと)うできるかを、見つめなおす必要もあるでしょう。このように、荘子の胡蝶の夢の例のように、物事を見る時一面から見るのではなく、複眼的に様々な観点から見る必要があります。
さらに、物事の全体像を捉える「俯瞰的視点」も重要です。「木を見て森を見ず」という言葉が示すように、一本の木にとって都合の良いことが、必ずしも森全体にとって最善の策とは限りません。短期的にはその木にとって最善の策であっても長期的に森全体にとって悪影響があれば、結局はその木にとって致命的な問題となるのです。
これらの視点を養うのは、幅広い教養教育です。教養教育は、単に知識の蓄積ではなく、広く柔軟な視点の獲得に繋がるものとして重要です。さらに、グローバル社会においては、人類の活動のフィールドはますます拡大していき、異なる言語、文化、民族、宗教、国の相手との関係構築、そして協働が必要となります。そのような状況に適切に対応するためには、孔子の言葉である、相手の心や立場を鑑みて物事を判断する「恕」の心、即ち「寛容の心」と、他者の異なる文化や考え方を理解・尊重する「共生の心」を育むことが重要です。そして、この前提として忘れてはならないのは、「己を知る」ことです。多様性を持つ人類が共存共栄していくためには、まず自己を知り、自国の文化を理解し、かつ尊重することが必要です。自分自身を、自国を愛することが出来なくて、それらを誇りに思うことができなくて、どうして他人や他国を理解し尊重することが出来るでしょうか?
皆さんは、大阪大学で思う存分学んで欲しいと思います。さらに積極的に自ら問題意識をもって回答を求める努力をして欲しいと思います。また世界に目を向けて欲しいと思います。積極的に海外に出かけて様々な国の人と交流して欲しいと思います。大阪大学には様々なプログラムや機会があります。是非ともこれらを積極的に有効活用して歴史的大変革期を生きてください。
夢を叶える:マッサンの夢、私たちの夢
皆さんは、今、大阪大学に入学という一つの大きな山の頂に立っているのです。皆さんはその頂に、どのような思いで立っているのでしょうか?ここまでの長い道のりを思い出しながら、感慨に耽(ふけ)り目の前の新しい景色を見つめているのかもしれません。あるいは、これから挑戦しなければならない、眼前に聳(そび)え立つ山々を仰いでいるかもしれません。皆さん一人一人が見ている景色は様々で異なることでしょう。しかし、皆さんに共通しているのは、その景色は皆さんが今まで見たこともない、経験したこともない景色であるということです。
私(わたくし)は、常日ごろ若い人と話す機会があると、「目の前の山を登りきる」ことの重要性を語ってきました。いくら山に登っても頂上まで登入りきらなければ頂上からの新しい景色を見ることはできません。皆さんの前には登るべき山として常に越えなければならない試練や困難、あるいは叶えたいと強く願う志や夢があるはずです。人は夢を心に、あるいは未来への希望を胸に目の前の試練や障害を乗り越えて行こうと努力し、そして目の前に聳(そび)えている山を登って行きます。
人生における山では、頂上に立って初めてその山の高さがわかります。何より重要なことは、たとえ登りきった山が低い山であったとしても、登りきることにより、今まで見たこともない景色を見ることができるということです。これから進むべき道が、挑戦するべき山が展望できるのです。人生における登山では、どこにも標識はありません。今、自分が何合目にいるのか、それは誰にもわかりません。頂上に立ったとき、「自分が頂上に立ったこと」を初めて知るのです。頂上は、それを求める努力をし、必ずあると信じている人の前に、突如(とつじょ)現れます。それは心の準備ができている人に突如訪れる「ひらめき」そのものです。
皆さんは本日晴れて1つの山の頂に立つことの喜び、その意味、そしてその先に広がる未来という素晴らしい景色を展望できることを実感しておられるはずです。1回でも苦しいプロセスを経て頂上に立つことができた人と、途中で下山した人では、大きな違いが生じます。今回の経験を忘れることなく、これからも目の前の山を一つ一つ登りきる努力を怠らず、目指すべき山の頂に立って欲しいと思います。長い人生では山もあれば、谷もあります。たとえ谷底に落ちても、それは次の山登りの絶好のチャンスと捉えて、次の山を、夢を目指せばいいのです。いつまでも未来への希望と夢を失うことなく、皆さんそれぞれの目の前の山を登りきってください。
3月末までHNKの朝ドラで放映されていたマッサンはニッカウイスキーの創業者で日本人初のウイスキー蒸溜技師の竹鶴政孝さんです。実はマッサンは大阪大学工学部の前身である大阪高等工業学校の卒業生です。マッサンは大正から昭和というあの激動の時代に大変な苦労と努力をして、目の前の山を1つ1つ登りきることにより、世界一のウイスキーを創るという、当時の日本では不可能と考えられていた大きな夢を実現させたのです。
「夢は叶えるためにこそある」
夢や理想は実現が困難だから夢であり理想と呼ばれます。現実と夢があまりにもかけ離れているが故に、人は夢を決して手に入れることができない遥か彼方の蜃気楼(しんきろう)だとあきらめてしまいます。しかし、夢を忘れることなく、夢に向かう努力を一歩一歩していると、いつの日か夢が現実のものとなります。 皆さんは未来という無限の可能性を持っています。どうぞ、この瞬間の、この感激を忘れずに、大いなる志と夢をもって、世界に羽ばたいてください。皆さんがそれぞれの夢を実現するための第一歩を大阪大学で踏み出されることを念じて私(わたくし)からの告辞とさせていただきます。
平成27年4月2日
大阪大学総長 平野俊夫