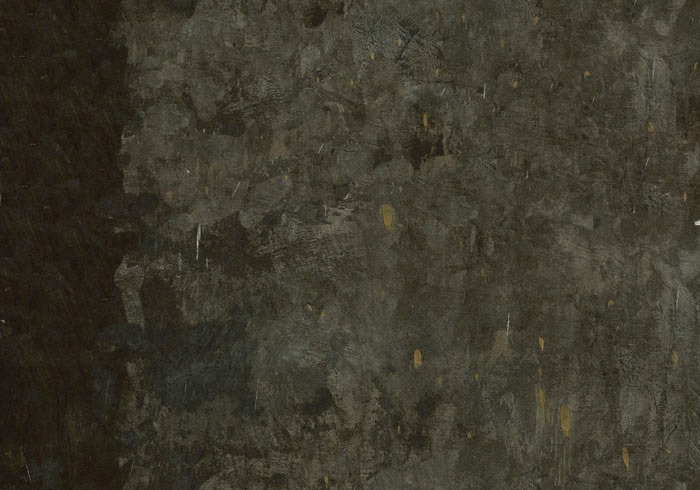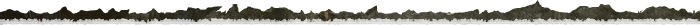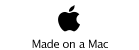免疫学と半世紀、Ver.1/2021_03_28
私の研究者人生の場であった日本免疫学会は、今年12月には創立50周年を迎える。50周年記念冊子を作成にむけて、歴代会長はインタビューを受けた。私自身も、自身の研究、学会の思い出、学会や若い人への期待、などの項目についてインタビューを受けた。過去50年は私の研究者人生そのものであり、時間の重みを改めて感じた。そのインタビュー記事を元に作成した思い出話を5回に分けてつぶやきに掲載することとした。
自身の生い立ちと研究について
大阪で生まれ、医者を目指して大阪大学医学部に入った。戦地から帰還した父は空襲で焼失した自宅の跡地で医院を開業した。私自身は焼け残った蔵の中で生まれた。父は往診時などに小さい私を同行することもしばしばあった。父は患者さんと話をするのが好きで私も患者さんに可愛がられた。幼少期は病弱で医者としての父の世話になることも多々あった。そんな環境に育った私に取り、医療は生活の一部であり空気そのものであった。私自身は生物に興味があり理学部に進学することも考えたが、父は私の進路に関しては何も言わなかった。結局、自然の流れで地元の阪大医学部に進学した。
写真:生後3ヶ月ごろ、父親に抱かれて
大学3年生になり、当時の一般教養科課程から医学専門過程に進んだ。しかし解剖学などいわゆる暗記ものばかりで退屈だった。そのような時に放射線基礎医学教授の近藤宗平先生の講義は衝撃だった。先生は物理学から遺伝学に転進された研究者で、阪大医学部に放射線基礎医学講座が設立された時に初代教授として三島の国立遺伝研から阪大に赴任された。先生の講義は理路整然としており大変興味深かった。最初の講義終了後、直ちに先生の研究室に押しかけて、そのまま研究のモノマネをさせてもらった。その後2年間ほど先生の研究室に通い続けた。このように、研究者になるきっかけは近藤先生からいただいた。
〜バイオリン、塩谷先生、山、家内との出会い、羽曳野病院の暗示、未来の暗示:作成中〜
大学3年生の時に、新設されたばかりの医学部山岳部に入部した。当時の医学部山岳部は、山岳部というよりはワンゲル部のようなもので、主として山歩きをした。その中で、もっとも印象に残っているのは、大学6年生の夏合宿である。静岡市から南アルプスに入山し、茶臼岳に登頂した。その後、聖岳、赤石岳、荒川岳をへて塩見岳まで縦走した。塩見岳で夏合宿は解散し、各々が自由に行動した。私は一人で塩見岳からバカ尾根と呼ばれている夏でもほとんど登山者がいない道を、途中ツエルトで一晩野宿し、2日かけて千丈岳まで縦走した。いつもお世話になっていた北沢峠の大平小屋で1泊したのちに、妹を迎えに戸台まで下山した。食料などを追加購入して、再び妹らと千丈岳に登山した。その後に甲斐駒ヶ岳からアサヨ峰を経由して鳳凰三山(地蔵が岳、観音が岳、薬師が岳)を縦走した。茶臼岳から南アルプスに入山して実に20日間後に下界に生還した。身も心も自然そのままになり、生き生きと生きている実感が体の芯から湧いた。また、大学3年生から5年生の冬休みには大平小屋を訪れ、晴天にも恵まれて3年連続元旦は千丈岳頂上で初日の出を見ることが出来たのは生涯忘れることが出来ない青春の思い出である。
写真:1970年元旦、南アルプス千丈が岳(3033m)頂上付近:背景は甲斐駒ヶ岳(2967m)
大学5年生の時に、山村雄一先生(元大阪大学総長、故人)の話を聞いて、免疫学に関心を抱いた。卒業間近に、近藤先生に免疫学に進みたいと相談すると、先生は免疫学をやるなら是非アメリカに行きなさいと言われた。卒業式を間近に控えた頃で、まだ医師国家試験受験勉強中だった。1972年3月に医学部を卒業し、まずは山村先生の第3内科に入局した。最初に受け持ったのは、自己免疫疾患のSLE(全身性エリテマトーデス)と肺がんの患者さんだった。文字どうり、患者さんと一体となり戦ったが、刀折れ、矢尽き、臨床医学の限界を体のそこから実感した。<目の前の医療よりも明日の医療のために医学を志そう> この思いはその後羽曳野病院での勤務を通じてもますます大きくなった。初心貫徹ということで、1973年に近藤先生の紹介で、アメリカに留学した。
アメリカ留学
留学先は、ボルチモアにあるDr. Takashi Makinodan の研究室があるGerontorogy Research Center (現National Institute on Aging, NIH)だった。直接のボスはAlbert A. Nordin先生だった。Nordin博士は大変柔和な人だったが、1984年にノーベル医学生理学賞を受賞したNiels K. Jerne博士の弟子で、博士のもとでプラーグホーミング方という抗体産生細胞を1細胞レベルで検出する方法を編み出した研究者だった。石坂公成先生の研究室に留学されていた、第三内科の先輩の岸本忠三先生(元大阪大学総長)や阪大癌研の高津聖志先生(現富山県薬事研究所所長、東大名誉教授)らに出会った。石坂先生はアレルギーを引き起こすIgEを発見され、ノーベル医学生理学賞間違いなしと言われた偉大な免疫化学の研究者だった(2000年日本国際賞受賞)。
当時の免疫学といえば、1960年後半にT細胞、B細胞が発見され、免疫イムノグロブリンを中心とする免疫化学の時代から細胞免疫学へと流れは大きく歩み出した時だった。1971年にワシントンで第1回国際免疫学会が開催され、DuttonがT細胞のかわりをする液性因子が存在することを発表、引き続き1972年にSchimpl と Weckerが T cell replacing factor (TRF)の存在をNatureに発表して注目を集めていた。ちなみに1971年に山村先生を中心として日本免疫学会が結成された。古くは1944年のMenkinによる内因性発熱因子、1953年のLevi-MontalciniらによるNerve Growth Factor、1965年のCohenらによるEpidermal Growth Facotr の存在の発見、1954年の長野、小島によるウイルス干渉現象の発見(インターフェロン存在の発見)、1965年のKasakura and LowensteinによるLymphocyte blastogenic factor、1966年のMigration inhibitory factor, 1967年のLymphotoxin、1976年のT cell Growth Factor (TCGF) の存在の発見など、各種活性を有する液性因子(サイトカイン)が存在することの発見が相次ぎ、1978年当時には、200種類以上の液性因子の存在が報告されていた。もちろんこれらの液性因子はすべて微量分子であり、その実体は全く不明だった。T細胞の抗原受容体も不明であり、その実体解明に向けて華々しい競争が繰り広げられていた。1975年にKohler and Milsteinによりモノクロナル抗体作成の報告がNatureに掲載されるとともに、1976年にはTonegawaらにより免疫グロブリン遺伝子再構成が発見された。大地震のまえの地底でのエネルギーの蓄積のごとく、エネルギーの蓄積が爆発、あるいは爆発寸前、ダイナミックな現代免疫学がまさにスタートしようとしている時だった。私自身は、留学中は、キラーT細胞に関与する液性因子の研究に取り組んだ。
写真:アメリカ留学時代の研究仲間と
〜パールハーバー、結婚、アメリカ大陸横断:家内はパールハーバーディにジョンエフ・ケネディ空港に降り立った:作成中〜
再び日本へ:結核性胸膜炎患者さんとの出会い羽曳野病院、熊本大学
1976年に帰国後、2年間大阪大学第三内科で半分臨床、半分免疫学研究生活を続けた後、1978年に大阪府立羽曳野病院(現、大阪はびきの医療センター)に出向することになった。現在は一般病床が1000床もある総合病院だが、当時の羽曳野病院はまだ結核療養所の名残りがあり、患者さんも、結核や呼吸器疾患、さらにアレルギー疾患の方がほとんどだった。羽曳野病院での私の上司は露口泉夫先生(元・羽曳野病院院長)だった。露口先生からは患者管理の手法をいろいろ教わったが、「胸膜炎の患者の胸水にはTリンパ球が非常に多い」という話は私の好奇心をいたく刺激した。胸膜炎の患者さんからは治療のため、1L近い胸水を抜くことも多々あった。胸水1Lの中に10億このリンパ球が存在している。そんな患者さんが病院には何十人といた。しかも胸水リンパ球を結核菌体成分で刺激すると、その培養上清中には非常に強い抗体産生誘導活性があった。当時はサイトカインの存在は知られていたが、その本体は全く不明だった。サイトカインを精製していた研究者はS.Gillisら世界でも数人だったが、なんとか精製ができないかと考えた。
昼間は病棟で患者さんの治療に専念した。午後5時以降に、同僚の寺西強医博(現大阪府守口市医師会会長)らと、昼間に治療目的で患者さんから得た胸水から夜中までかかってリンパ球を分離し、生理活性分子を得るために結核菌体成分と一緒に2日間培養した。培養上清を冷凍保存し、週末などに時間を見つけては実験を行なった。抗体産生誘導活性は自分自身から得たBリンパ球や、Epstein Barr Virus (EBV)で細胞株化した自己Bリンパ球由来B細胞株に加えて培養することによりを確認した。精製することを最終目標として、様々なタンパク分離手法を用いて生理活性物質の性状解析を続けた。昼間は臨床、夜と週末は研究に明け暮れた20歳代最後の無我夢中の2年間だった。
そろそろ阪大に戻れると思った12月ごろ、羽曳野病院の詰め所でカルテを整理していたところに当時阪大総長に就任されていた山村先生から、「明日、総長室に来るように」と電話があった。総長室に行くと「学校の先生になる気はないか」と突然いわれ、一瞬なんのことか理解できずに戸惑った。熊本大学に新設された免疫生化学教室に山村先生の弟子の尾上薫先生が教授に就任されるので、助教授を探しておられた。要するに助教授として熊本に行かないかということだった。後先のことを考えることもなく、その場で即答してしまった。1980年、32歳、基礎研究にどっぷりつかることになった。決断をしたというよりは、自然の流れの中に身を任せた。研究に専念できるという、未来が開かれた。
写真:大阪府立羽曳野病院勤務時代
熊大では、守衛さんに学生と間違われもした。しかし、朝から晩まで研究に専念できる環境があった。熊大でも後のIL-6につながる液性因子の研究とそのタンパク精製をつづけた。リンパ球は、熊本市内の耳鼻咽喉科の先生方に頼んで、扁桃腺切除した患者から集めた。ただひたすら研究に没頭した。1984年まで約4年間過ごした熊本は第2の故郷である。次女も熊本大学病院で生まれた。熊本大学での研究により、生理活性分子の性状として、等電点5で分子量2万分ということが明らかになってきた。1983年に京都国際会館で開催された国際免疫学会でも発表する機会があった。しかし、普通のタンパクの精製とは異なり、その活性はあくまでもBリンパ球に加えて数日間培養し抗体産生がどの程度生じるかを測定するしか手段はなかった。種々のカラム操作で分離して得られた資料を全て培養液に置き換えるとともにフィルターでろ過して無菌化する必要があった。このような操作は単純作業だが、サンプル数が多く大変だった。さらに操作のたびにタンパクが吸着などにより消失していく。精製すればするほど目的の物質は少なくなり、挙句の果ては活性すら追跡不可能になる。まさに牛歩のごとく前に進まなかった。
写真:熊本大学医学部助教授時代
1979年から1980年にかけて、谷口維紹先生(東京大学名誉教授)によるインターフェロンベーター、Shigekazu Nagata, Charles Weissmannらによる インターフェロンアルファーの遺伝子クローニングの成功というサイトカイン研究史におけるマイルストーンといえる事件があった。当時の私にはインターフェロンは免疫とは関係ない遠い世界の出来事に思えたが、1983年の谷口先生によるIL-2遺伝子のクローニング成功の大ニュースを新聞で知り、少なからず衝撃を覚えるとともに、私と同世代の若い研究者の存在に深い敬意を評するとともに、いつかは追いつきたいという思いが沸いてきた。また岸本先生らが阪大で、B細胞に作用する因子として、B 細胞分化因子(BCDF:IL-6) や、B 細胞増殖因子(BCGF)の同定の試みを精力的にされていた。また高津先生が、現在のIL-5(当時TRFと呼称)の研究を、William Paul やM. Howardらが現在のIL-4に相当する因子の研究を行うなど、B 細胞に作用する液性因子の同定はまさに国際的な競争下にあった。私自身も、遺伝子工学手法を取り入れようと考えていろいろ試行錯誤を繰り返していた。そのころ、阪大細胞工学センター教授に就任された岸本先生から「一緒にやらないか」とお誘いがあり、助教授で阪大に戻ることにした。当時、岸本先生はB細胞に抗体産生を誘導する液性因子の研究をしておられ、競争相手でもあった。
阪大へ、インターロイキン6へ
1984年1月から岸本先生と共同研究を開始し、それまでの長年の経験を生かして、1984年末には電気泳動でシングルバンドまで精製することができた。そして阪大タンパク研の綱澤進先生と一緒に液性因子のN末端の13個の部分的アミノ酸配列決定に成功し、遺伝子単離も時間の問題と思った。1985年は素晴らしい年になることを確信した。しかし、それからが生みの苦しみが始まった。1985年は散々の年だった。2月に父親を亡くし、8月には日航ジャンボ機が墜落した。仲間の弟さんや阪大教授も犠牲者になった。なんともやるせない暑い夏であった。研究にも暗い影がただよった。N末端のアミノ酸配列をプローブに抗体産生を誘導する液性因子の遺伝子クローニングを続けていたが、来る日も来る日も目的を果たす事ができなかった。「N端の部分的アミノ酸配列が間違っていたのではないか?」という不安が常につきまとった。しかし、そのことを証明する術は、遺伝子をクローニングしない限り無かった。底なし沼である。信じる者のみが進むことが出来る暗夜である。
一燈を提げて暗夜を行く。
暗夜を憂うることなかれ。
ただ一燈を頼め。ーーー 言志四録
度重なる失敗によるストレスと疲労が重なり、1985年の年末にはひどい不整脈になり眠れなくなった。研究者の道をあきらめようかとも思った。
1986年、年明けに友人の循環器専門医に診てもらったら、「心因性」と言われた。こんなことで、人生棒に振るわけにはいかないと思い直し、100リットルのリンパ球培養上清を集めなおし、一から精製を始めた。居直ったら気持ちが軽くなり、10日間ぐらいで不整脈は治った。2月に本庶佑先生(2019年、ノーベル医学生理学賞受賞)らがIL-4遺伝子を同定したことを発表された。我々が同定を目差している因子は彼らが同定したIL-4と同じ分子ではないかという恐怖が襲った。今から思えば、このときは山の頂上の直下、息を切らしながら頂上を目差す登山者のそれであった。頂上が目の前にあることはまだわからない。息絶え絶えの状態であった。研究室では、我々の研究継続が危ぶまれる事態に追いやられた。しかし、気にせずに山の頂上を目指し無我夢中で研究をつづけた。
3月に、再び液性たんぱく質を精製することができた。N末端の配列だけに基づいたプローブだと従来と同じだと思い、“賭け”にでた。精製タンパクを限定分解して得られる複数のペプチドのN末端配列を同定することにした。限定分解したペプチドを分離するためのカラム操作により全てを失うリスクがあった。まさに「ハイリスク ハイリターン」である。当時は研究室にもいづらくなっていたので、だめなら研究室を去る覚悟を決めた。幸いにも、プローブ作成に使用できそうなN末端配列を有する3つの限定分解産物を得ることができたので3種類のプローブを作成して遺伝子クローニングを再開した。
1886年の5月の連休のころは重苦しい精神状態で、連日クローニングの実験に取り組んだ。今、9号目にいるのか、はたまた3号目にいるのか?自分の立ち居位置は全くわからない。その時頂上は突如目の前に出現した。1986年5月25日、日曜日の午前11時に研究室に来て、暗室でフィルムを現像すると、三つの異なるプローブと結合している遺伝子が3万のクローンの中から1つだけ確認できた。羽曳野病院で精製を開始してからじつに苦節8年、夢にまで見た遺伝子を手に入れた瞬間である。その日の午後、一緒に苦楽を共にしていた保川清君(現京都大学教授)、渡部保夫君(現愛媛大学名誉教授)、松田正君(現北海道大学教授)に大学の近くの喫茶店に来てもらった。興奮しながら今後の実験計画を立て、休む間も無く次の実験に取りかかったのがつい昨日の様に思える。
写真:IL-6遺伝子:3万個のcDNAライブラリー中一個のクローンのみが3種類のプローブと結合しているのが確認できた。
写真:1986年夏の研究室旅行ではしゃぐ平野。この姿でこの直後にプールに飛び込んだ!
1986年夏にトロントで開かれた国際免疫学会で発表したが、学会中もホテルに閉じこもりひたすら論文を書いた。帰りの機内でも論文作成を続け、帰国後すぐに投稿した。幸いにも我々の 研究成果は1986年11月6日号のNature誌に高津先生と本庶先生らのIL-5遺伝子クローニングの研究成果とともに掲載された。同じ年の9月に26kDa 蛋白の、10月にはインターフェロンベーター2のクローニングの報告が、Eur. J. Biochemistry とEMBO J にそれぞれ掲載された。驚いたことにこれらの分子はすべて同じ構造をしていることが判明した。なんと、EMBO Jの論文は1986年5月末に投稿されている。あと1ヶ月論文投稿が遅れていれば、我々の論文はNature に掲載されなかったかもしれない。トロントで開催された国際免疫学会中もホテルに閉じこもり論文執筆をしなかったらどうなっていたことか!研究における競争という厳しい現実を心の底から実感した瞬間でもあった。かくして、1986年は私の人生で最もホットでかつ目まぐるしい展開を遂げるとともに、終生忘れることが出来ない1年となった。 その後、ミエローマプラズマサイトーマ増殖因子や、肝細胞刺激因子など種々の分子は、すべて我々がクローニングした分子と同じものであることが明らかになった。各々のグループが異なる名称を使用していたので、1988年のニューヨーク・アカデミーの主催する国際会議においてインターロイキン6という名称に統一された。かくして、Interleukin 6(IL-6)という名前が世に誕生した。
写真:ニューヨーク科学アカデミー紀要表紙
1992年にハンガリーのブタペストで開催された第8回国際免疫学会で、Jack L. Strominger博士、岸本先生とサンド免疫学賞(現在のノバルティス免疫学賞)を共同受賞する感激を味わうことができた。夜のドナウ川に映る街灯の美しさが星のきらめきのごとく脳裏に焼き付いている。
写真4:サンド免疫学賞
この間、当時細胞工学センターの教授をされていた谷口維紹先生にはいろいろ教えていただき、公私ともに大変お世話になった。大学近くのマンションへの夜道を谷口先生と語りながら歩いたのが懐かしく思い出される。
研究室を持つ
1978年から1989年の約10年間は、暗夜をさまよいながらも、なんとか1つの山の頂上に立つことができた。追い求めていたIL-6が単にBリンパ球に作用して抗体産生を誘導する作用以外にも、急性期タンパクの産生誘導や多発性骨髄腫の増殖誘導活性など様々な細胞に作用する多機能分子であるということが明らかになった。頂上に立ち初めて見た新しい景色であった。さらに頂上からは次に進むべき道、次に登るべき山が展望できた。1989年11月に大阪大学医学部教授に就任し新たな出発点に立った。
長い道のりの果て ついにいま、確かな一歩を
果てしのない道が再び目の前に
そのはるか彼方に 希望の星が静かに輝いている
踏み出そう、勇気をもって 新たな第一歩を
研究室は大阪市の中心部の中ノ島の懐かしい旧阪大医学部にある旧蛋白研の古い建物の中にあった。1年後には吹田の新しい医学部キャンパスに移転の予定のため、古い建物にある研究室は、雨漏りすれども、抜本的な修理は行われず、応急的に天井にブリキ缶を吊るし、ゴム管でたまった雨水を窓の外に誘導するというものだった。かくして我が研究室は雨ともなると優雅な雨垂れの音楽が響き渡るという状態だった。それでも窓の外に咲き誇る満開の桜の花は目に染みた。
遠心器音なり出せば心打ち眼にしむ桜あでやかに舞う
写真、1992年ごろ、医学部教授室で
中嶋弘一君(元大阪市立大学医学部教授)、松田正君(現北海道大学薬学部教授)、改正恒康君(現和歌山大学医学部教授)らと、インターロイキン6の作用機構の解明に向けての非常に地味な、しかし重要な研究を開始した。また、この頃に、関節リウマチなどの自己免疫疾患や慢性炎症性疾患の発症モデルである局所引きがねモデル(Local Initiation Model)のプロトタイプを提唱した。すなわち、感染、損傷、結石などの異物など、局所での非免疫組織における慢性的な出来事が引きがねとなり、免疫系との相互作用により慢性炎症が持続的に引き起こされた結果として、関節リウマチや動脈硬化症などの自己免疫疾患や慢性炎症性疾患が生じるのではないかという仮説である。IL-6受容体を介して少なくとも2つのシグナル伝達、すなわち、STAT3を介するシグナル伝達経路と、SHP2/GAB/MAPKを介するシグナル伝達経路が活性化されることを証明するとともに、それぞれのシグナル伝達経路が細胞の増殖や、分化、生存、細胞運動にどのように関与しているかを明らかにした。さらに、これらのシグナルが生体内でどのような役割を果たしているかを明らかにするために、gp130(IL-6受容体のサブユニット)を介するそれぞれのシグナルのみを特異的に欠失した変異gp130を発現しているマウスの作成を試みた。そして2000年、大谷卓也君、日比正彦君(現名古屋大学理学部教授)らとレセプターの点変異マウスの作成に成功、試験官内のみならず、生体内でのインターロイキン6の作用機構の解明に成功した。単なる遺伝子のノックアウトの手法では解明することが困難であるとされていた、特定のサイトカイン受容体を介する特定のシグナルの生体内での役割を明らかにすることができた。この間、山中庸次郎君(カナダトロント大学)、伊藤素行君(現千葉大学薬学部教授)、深田俊幸君(現徳島文理大学教授)、西田圭吾君(現鈴鹿科学大学薬学部教授)、藤谷与士夫君(現群馬大学教授)ら多くの優秀な大学院生が育つとともに、臨床教室から研究に参加した織谷健司君(現国際医療福祉大学教授)、武田卓君(現近畿大学医学部教授)、松村到君(現近畿大学医学部教授)、草深隆志君(故人、元日本大学医学部教授)らが立派に育つという幸福感を味わうことができた。
事実は小説より奇なり
IL-6遺伝子クローニングから14年、ドラマは2度訪れた。石原克彦君(現川崎医科大学教授)、熱海徹君らによる、IL-6レセプターの点変異により関節リウマチのような自己免疫疾患が発症するという発見である。関節リウマチなどの自己免疫疾患は複数の遺伝要因と環境要因により発症する難病で、その原因はいまだ不明だ。1987−88年にかけて、心房内粘液腫の患者に観られる自己免疫様症状が、粘液腫を摘除することによって消失することに注目し、粘液腫が産生する何らかの因子が関与している可能性を考え、その因子の本態がIL-6であることを明らかにした。また、関節リウマチ患者関節液中には、IL-6が著増していることを見つけ、IL-6が自己免疫疾患に関与しているのではないかと考えていたが、決定打はなかなか得ることはできなかった。いろいろモデルを考え、IL-6と関節リウマチのような自己免疫疾患の関係を明らかにする努力を模索しつつも失敗の連続で、このことは一日とも私の脳裏を離れることはなかった。1990年代に中嶋弘一君や日比正彦君らとIL-6受容体を介するシグナル伝達機構の研究を行い、それぞれのシグナルを欠損しているIL-6受容体を発現しているノックインマウスを作成した。2000年に石原君、熱海君らが、SHP2シグナルを欠損している変異gp130を発現しているノックインマウス(F759マウス)は、gp130を介するSTAT3シグナルが亢進しているとともに、加齢により自己抗体を産生し関節リウマチ類似の関節炎を発症することを見つけた。最初に報告を受けたときには、にわかには信じられなかった。確かにIL-6シグナルが異常になっているgp130F759マウスは、老化とともに、例えばプラズマ細胞腫のような何らかのがん性病変をきたすことは期待してはいたが、関節リウマチのような複数の遺伝子や環境要因がからんでいる自己免疫疾患がIL-6 の単独の異常だけで自然発症することは、願望であっても、考えがたかった。しかし、まさに“事実は小説より奇なり“、まぎれもなくIL-6シグナルルの異常で関節リウマチ様の関節炎が自然発症した。興奮して眠れない日々が続いた。ついに、IL-6などのサイトカイン受容体シグナル異常により自己免疫疾患を発症することを証明したのだ。サイトカインと自己免疫疾患発症の機構を考える上で、非常に重要な知見がもたらされた。一方、中外製薬の大杉義征博士らは、阪大の岸本先生らと共同で、IL-6阻害剤であるIL-6受容体抗体を関節リウマチの治療薬として開発した。我々の基礎的な研究により、抗IL-6受容体抗体が関節リウマチに効果があることに対して、科学的根拠を示したのみならず、なぜIL-6の異常で関節リウマチなどの自己免疫疾患が発症するかの機序を解明する道が開けた。
IL-6 アンプと局所引きがねモデル、そしてサイトカインストーム、COVID-19へ
その後、村上正晃君(現北海道大学教授)らがIL-6の異常でなぜ自己免疫疾患が発症するかの仕組みの解明をおこなった。2006年には澤新一郎君(現、九州大学教授)と村上君により、免疫システムと非免疫システムの相互作用により関節リウマチのような自己免疫疾患が発症するのではないかという1990年代はじめに提唱したモデル(前述、Local Initiation Model)を証明することができた。さらに小椋英樹君(現在留学中)と村上君らの努力により、IL-6とIL-17が非免疫細胞に作用して、STAT3とNF-kBの活性化を介して相乗的にIL-6の遺伝子発現を誘導するとい事実が明らかになった。乃ち、IL-6の増幅回路(IL-6アンプ)が存在することを見つけるとともに、関節炎の発症に関与していることを明らかにすることが出来た。さらに抗原特異的なT細胞が関与するような自己免疫疾患においてもIL-6アンプガ関与している事を示した。さらに、IL-6アンプはIL-6のみならず、炎症性サイトカイン産生の増幅機構であり、自己免疫疾患や動脈硬化などの慢性炎症疾患、そしてがんの発症に関与していることを明らかにした。新型コロナウイルス感染症の重症化に関与するサイトカインストームにもIL-6アンプが関与している可能性を提唱した。そして、1年半ほどかけてIL-6研究の総説論文を完成することもできた。
T. Hirano, IL-6 in inflammation, autoimmunity and cancer. Int. Immunology 33:127-148, 2021.
研究には失敗も数え切れないくらいあり、実験結果に失望することも多々あった。まさに紆余曲折の連続であった。そのような研究者人生で嬉しかったことの1つは、2009年にスウェーデン王立科学アカデミーからクラフォード賞を受賞したことである。“インターロイキンの発見、それらの特性決定と炎症性疾患における役割の探求”という基礎的研究が関節リウマチなどの炎症性疾患に対する治療薬開発への道を開いた事が評価されて、アメリカコロラド大学のCharles Dinarello教授、岸本先生、そして私の三人が共同受賞した。クラフォード賞は、人工腎臓の発明者であるホルガー・クラフォード及び、彼の妻アンナ=グレタ・クラフォードによって設立されたクラフォード財団がスポンサーとなり、スエーデン王立科学アカデミーが1982年に創設した賞である。
2007年5月11日−13日の3日間、クラフォードディがストックホルムと大学の町ルンドで開催された。11日は王立科学アカデミーで国王、王妃ご臨席のもと、授賞式が開催された。国王から直々にメダルと賞状をいただき、固い握手を交わした(図13−16)。アバのダンスィングクイーンの合唱歌が会場に響きわたった。 そして、晩餐会、国王と同じテーブルに着席、食後のティータイムは王妃と親しくお話をする機会を得た。2日目はカロリンスカ研究所ノーベル講堂で学術講演会があり、受賞者がそれぞれ50分の講演を行なった。3日目はルンド大学で一般向けの30分の講義(Crafoord Prize Lectures)、学生からの質問、記者会見をこなした。ルンド大学では、 “How extensive a view from the top of the mountain is!”という演題で講義をおこなった。
クラフォードディは私の30年の研究者人生が3日間に凝縮された決して忘れる事ができない時間であった。荘周のように“胡蝶の夢”を見ていたのか?(図19) 山村雄一先生の言葉“夢見て行い 考えて祈る”(図20)を胸に37年、自己免疫疾患の本質に迫りたいとう卒業当時の夢がインターロイキン6の発見により現実のものとなった瞬間でもある。クラフォードディが昨日の出来事のように思い出される。
写真、2007年、クラフォード賞記念撮影(中央。グスタフ16世スウェーデン王とシルビア王妃)、
写真、2007年クラフォード賞受賞講演、カロリンスカ研究所ノーベル講堂
写真、2007年クラフォード賞、記者会見
IL-6受容体に対する抗体医薬「トシリズマブ;商品名アクテムラ」等の、IL−6阻害薬が重症の新型コロナウイルス感染症治療に有効である事が、2021年1月にイギリスの研究グループなどにより明らかにされた。免疫学会創設50周年、IL-6発見35周年である記念すべき2021年に、IL-6阻害薬が重症の新型コロナウイルス感染症の治療に有効である事が明らかになった。長年の研究がこのような形で世の中に貢献できた事は、研究者冥利に尽きる。
目の前の山を登りきることが重要
研究室の若い人たちに例え話として山登りの話しをする。登山家は「どうせ登るのなら高い山に登りたい」と考える。しかし、私たち研究者にとっては、山が高いか低いかは登ってみないことには分からない。斬新な研究だと思っていたものがつまらなかったり、途中で投げ出したくなったりするかもしれない。しかし、「目の前の山を登りきる」ことが重要だ。
頂上を目指して歩いているときは、頂上では、どのような景色が展望されるのは全くわからない。山の頂上に登り切って初めて目の前に新たな景色が広がる。頂上にたって初めて自分が登った山の高さがわかる。その山は予想に反して低いかもしれないし、高いかもしれない。たとえその山が低くても頂上に立てば、目の前に素晴らしい高山がそびえているかもしれない。新たな予期しなかった秀峰がそびえているかもしれない。次に進む道が、めざす山が見えるはずだ。頂上近くになるときつくなりあきらめようとする。頂上近くが、登山において最もしんどい時だ。脱落の危険性が最もあるときだ。しかし、富士登山であれば、標識があり9合目に位置していることがわかる。いかに疲労困憊していても怪我や病気でもしない限り頂上に立つことができる。しかし人生や研究においては、未踏峰と同じくどこにも標識はない。今いる位置が9合目か、3合目かは誰にもわからない。学生の時、無人小屋を目指して縦走していたことがある。午後9時になり疲労も重なり小雨も降り出したのでビバークした。翌朝目がさめると200m先に無人小屋が静かに立っていた。
最後の1合目を乗り切ることは言葉では表現できない困難を伴う。それを乗り切ったときに初めて頂上のなんたることが明らかになる。中途半端でいくつもの研究を投げ出すと、いつまでも中途半端な研究者にしかなれない。たとえ100回山を登っても、一度も頂上に立ったことがない人は、たとえ1度でも頂上に立つことができた人には決して及ばない。たとえ低い山でも頂上に立つことができた人のみが新しい景色を見ることが、更なる展開をつかむことができる。これは研究だけではなく、我々の人生すべてに共通する事だ。
IL-6がB細胞に作用して抗体産生を誘導する以外にも肝臓の細胞に作用して急性期蛋白の産生を誘導したり、多発性骨髄腫の増殖因子であるというのは、予想していなかった事実だ。1988年に関節リウマチの患者さんの関節液中にIL-6が多量存在していることを見いだし、IL-6が関節リウマチの病態に関係しているのではないかということが想像されたが、このようなことは、研究開始時点では想像すら難しく、研究の結果、頂上まで登って初めてわかったことだ。IL-6が関節リウマチ関節液中に多量存在しているからといってもIL-6がリウマチの原因なのか、それとも副次的なものかはわからない。地道な研究の結果、IL-6受容体のある部位にミューテーションを入れたマウスは加齢により自然に関節リウマチ様関節炎になることがわかった。IL-6のシグナル異常により関節リウマチが発症するということを証明できた。さらに、IL-6増幅回路(IL-6アンプ)が存在し、この異常がサイトカインストームを引き起こすことがわかった。IL-6阻害剤が関節リウマチや、白血病のCAR-T治療におけるサイトカインストームや新型コロナウイルス感染症の重症化に効果があることが明になり、社会に貢献できたことは研究者冥利につきる。
山村雄一先生が1990年6月に亡くなられる2ヶ月前の4月に先生からいただいた色紙がいつも私の目の前にある。
樹はいくら伸びても 天まで届かない
それでも伸びよ 天を目指して
近藤宗平先生や山村雄一先生らの指導者や多くの共同研究者に恵まれたこと、家族の理解があったこと、多くの幸運に恵まれたこと、半世紀にわたり研究を続けることができたことを、ただただ感謝するのみ。“天の時、地の利、人の和”が私を今へ導いてくれたことを心の底から思うのみ。
写真:
免疫学会の思い出
私の免疫学会とのかかわりは、免疫学会を創設された山村先生の第3内科に卒後すぐの1972年に入局して免疫学の道を歩み始めたことから始まった。以来、免疫学会50年の歴史は、まさに自分の研究者人生と重なる。
免疫学会の思い出として浮かぶのは、まず1988年から3年間務めたニュースレターの編集長時代。多くの会員が参加できるニュースレターにしたいと思い、「オープン」をキーワードにした。これはのちに免疫学会長、阪大総長、そして現在の量子科学技術研究開発機構(量研/QST)理事長になっても貫いてきた姿勢で、若い人にも自由に、積極的に書いてもらった。
今でも読み返すほど有意義なものとしては、ネットで展開した公開討論会「独創的研究とは」だと思う。編集長を退任する最後の号(8巻第2号、通巻15号)に吉村明彦先生(現、慶応義塾医学部教授)が「独創性とは何か、あるいは優れた仕事を成し遂げるには何が必要か」というエッセイを投稿された。最終校正原稿を印刷所に送ろうとした矢先に、本庶佑先生から一本の電話があった。「ニュースレターに意見を書きたい」という趣旨だった。でも印刷は間に合わないので、ネットで標題の公開討論会を開くことにした。
当時は、ネット上での意見交換は大変珍しく、公開討論会では各自の思いのこもった熱い議論が交わされた。石坂公成先生も投稿されるなど4か月の間に13人16件の意見が寄せられた。この中には、「オンリーワンになることが独創性への最も近道である」という本庶先生の言葉など各先生の研究に対する哲学、考え方など至極の言葉がちりばめられている。幸い、今でもネットに残っているので、ぜひ読んでもらいたい(日本免疫学会ホームページ -> 一般の方へ -> JSI Newsletterのサイトにリンクあり)。
2005年に日本免疫学会会長に就任した。前任の高津会長時代に、それまでの任意団体から特定非営利(NPO)法人になることが決定された。私の役割はNPO法人としての学会のスムーズな立ち上げと、2010年に日本で開催される国際免疫学会の準備体制を整えることであった。また、引き続き情報発信にも努めた。高津会長時代に学会の財務改革が行われた。それまでは、学術集会の財務管理は学術集会長の責任で行われていたが、免疫学会事務局が責任を負う形に改革された。さらに、私の時代には、学術集会のプログラム策定に関する改革を行った。それまでは学術集会の会長の裁量で決めていたので、学会として一貫性があるとは必ずしも言えなかった。学術集会に一貫性を持たせるために、学会の学術委員と学術集会の委員との合同で、プログラムや学術集会のやり方などを決めることにした。新しい体制下での初めての日本免疫学会学術集会(第36回)を、学術集会長として2006年12月に大阪国際会議場で開催した。
写真:第36回日本免疫学会学術集会懇親会、大阪リーガロイヤルホテル
左から、高津聖志先生(第13代会長(、宮坂昌之先生(第15代会長)、平野(第14代会長)、W. Paul 博士(元アメリカ免疫学会会長)、
肺がんになる:人は必ず死ぬ
〜作成中〜
医学部長から阪大総長へ
〜作成中〜
総合科学技術会議
〜作成中〜
量子科学技術研究開発機構(QST)理事長
〜作成中〜
免疫学から量子生命科学へ、若い人へのメッセージ
50年ほど前に、免疫学が免疫化学の時代から細胞免疫学の時代へと転換したように、今また、免疫学の新しい時代が始まる大きな転換期を迎えていると思う。システムバイオロジーや量子力学など、新たな視点を取り込むことにより、免疫学は新しい時代を迎えさらに発展していくと思う。
次の50年に何を目指すかを模索してほしい。異物が体内に入ってきて、花粉症にしても新型コロナウイルス感染症にしても、ある人は症状がでるが、ある人はでない。その程度も様々であるし、がんに対する免疫応答も人それぞれである。個々の人の免疫応答を予測可能にするためには、免疫システムの統御機構を究極まで追求していく必要がある。
分子生物学の進歩と共に免疫学は大きく花開いた。また、免疫学は生命科学全体を牽引してきた。我々は体のすべての部品の設計図を手にした。自動車は10万点の部品を分解し組み立てても再び動く。しかし、生命はそうはいかない。免疫学は、今でも日々新たな知見を得ているし、これからも数多くの免疫を利用した治療薬が開発されると思う。しかし分子レベルでの生命科学には限界があり、「命とは何か?」という究極の疑問には無力である。
私が理事長を務める量研/QSTでは、スピントロニクスなど量子科学技術に基づいた理工学領域に加えて、放射線生物学や医学などの領域がある。これらを融合し、量子レベルや、量子力学の視点で生命現象を観た時に新たな発見やブレークスルーが起こると考えている。
16世紀に光学顕微鏡が登場し、分類学だった生物学にパラダイムシフトが起き、細胞生物学の時代が花開いた。生命科学は科学技術に大きく依存している。量子科学技術に基づいた最先端の観察・計測技術を応用すれば、観察したことがない現象が見つかる可能性がある。
渡り鳥は地磁気を検知して3,000kmも飛来することができる。その仕組みには「量子もつれ」が関与しているようだ。光合成は「量子重ね」、酵素反応は「量子トンネル」が関与しているようだ。麻薬犬やサメなどの鋭敏な嗅覚機序は、分子生物学的には確立されているが、このような高感度を説明するには量子力学の観点の研究が必要である。
このような考えにたち、量研/QSTの組織再編を行い「量子生命科学研究所」を新設すると共に、量子免疫研究チームも作った。また「一般社団法人量子生命科学会」を2019年に創設した。今後、免疫学会との連携も進めたい。
免疫学会は若手研究者に夢を与える学会になってほしい。夢は、人や組織にとって異なるが、共通することはその人や組織に取り実現困難だという事。しかし夢と諦めてしまえば永久に夢に終わる。「夢は叶えるためにある」と思う。夢に向かって目の前の山を1つ1つ登り切っていくことが重要。そうすれば夢は、突如、現実のものとなる。夢にたどり着けなくても、夢を目指す1つ1つの努力、その過程が人生を豊かにしてくれる。目の前の山の頂上に立つことにより、それが例え低い山であっても、新しい景色が見える。次に進むべき道が、次に登るべき山が見える。そして、その先に夢が静かに待っている。
自分の研究成果は決して一人で成したことではなく、共同研究者はもちろんのこと、無数の先人たちの多くの努力の結晶の上に、己の研究があることを自覚して、謙虚さと感謝の心が大事だと思う。己に驕ることなく、謙虚に己を見つめ、己を磨くことが、次なる飛躍に、ブレークスルーに導いてくれる。
また、「己に誇りを持つ」が大事だと思う。己に自信がなければ、己に誇りがなくては、人は他人の成功を心から喜ぶことはできない。むしろ妬んだり、足を引っ張ろうとする。誇りを持つためには己を磨かなければならない。己を磨くためにも己を知る必要がある。己を知ることにより、謙虚な心が生まれ、己を磨くことにつながる。自然は果てしなく大きく、人間の理解をはるかに超えている。
「己を知り、己を磨き、己に誇りを持つ」
「夢は叶えるためにある」
を胸に、人生を歩み、真理解明を目指してほしい。
新型コロナウイルス感染症に思う
2019年12月に中国で発症した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、パンデミック感染症となり、一年ほどの間に世界中の感染者は1億2千万人、死者は270万人を突破した。
新型コロナウイルスは、いみじくも私たちに、「世界は1つである」こと、「国境はないこと」を教えてくれた。最近芽生えつつある、グローバル化から一国主義、協調から対立へ、信頼から疑心暗鬼への流れに新型コロナウイルスは警鐘を鳴らしている。世界は協調しなければ新型コロナウイルス感染症を克服することはできない。「地球市民」としての自覚と、「相手の立場を尊重し、信頼し、助け合う、連帯と協調の精神」が重要だと思う。
人類の歴史は多様性ゆえの発展と対立の歴史であった。多様性ゆえに心豊かな生活を送ることができる。また、多様性はイノベーションの源泉でもある。一方、多様性ゆえに対立や紛争、そして幾多の戦争を経験してきた。一方、学問、科学技術、芸術やスポーツは人類共通言語であり、多様性の壁を乗り越える大きな力を有している。私たちは、宗教や言語が異なっていても、これらの人類共通言語を介して心を通じ合うことができる。人類共通言語により、私たちは多様性の壁を乗り越えて、世界中の多様な人々と交流し、異文化理解や異文化尊重を育むことができる。その先に、平和で心豊かな人類社会の発展がある。インフルエンザウイルスやコロナウイルスなどの感染症も、また多様性の壁を楽々と乗り越える。感染症はある意味で人類共通言語であるとも言える。このような時だからこそ、「調和ある多様性の創造」は、かってないほど重要になっている。人類の命運がかかっている。
COVID-19パンデミックにより人類社会は大きな変革の波に襲われている。このような大波は20万年の人類歴史上、少なくとも4回はあったと思う(表1)。20万年前から1万年前まで続いた最初の大波では、東アフリカに誕生した現生人類(ホモ・サピエンス)が世界に拡散した。人類史上最初のグローバル化である。その過程で現生人類は5万年ほど前にネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルターシス)と交雑した。現生人類に滅亡させられたネアンデルタール人由来の遺伝子がCOVID-19重症化や抵抗性に関連していることが明らかにされている。そして1万年ぐらい前に農耕文明とともに始まり13世紀まで約1万年続いた第2波では、言語、人、習慣、宗教などの現在の多様性の基盤が確立された。さらに家畜化された牛などや、生活圏にある小動物や蚊などから天然痘、麻疹、結核、ペスト、マラリアなどの感染症が人類に伝播され感染症の多様性基盤も確立された。400年間ほど続いた第3波では、13世紀にモンゴル帝国が設立され大航海時代が始まり、世界が7つの海で繋がり世界はグローバル化した。その過程で、感染症が世界に拡散し、暗黒の中世ヨーロッパにおけるペストの流行と封建体制の崩壊や、ヨーロッパからもたらされた天然痘によるアステカ帝国やインカ帝国の崩壊が起こった。そして18世紀に産業革命とともに始まり200年間続いた第4波では、科学技術革新が凄まじいスピードで進み、世界覇権競争の結果として世界大戦を2度も経験した。この時期には病原菌の発見、予防注射の発見や抗生物質の発見など感染症との戦いの歴史が繰り広げられ、人類は感染症をある程度克服できるようになった。その象徴として1980年の世界保健機関(WHO)による天然痘撲滅宣言がある。1989年のベルリンの壁崩壊を契機に第5波に入ったと考えられる。それは移動手段や情報伝達手段などの著しい進展や人口増加による相対的な地球狭小化がもたらす多様性の爆発である。このような状況下でCOVID-19が世界を襲った。世間ではポストコロナの時代はどうなるかということが大きな話題になっているが、歴史の大きな流れの中ではCOVID-19は第5波の中で生じた単なる1つの出来事にしかすぎない。我々は今、第5波の中に位置していることを念頭に、世界は、国は、大学や研究機関は、企業は、そして個人は、どのような考え方に立ち、第5波を生きていくかを考えないと太極を見誤る。
COVID-19は環境問題でもあるという認識が重要
18世紀に始まった第4波では科学技術革新が急速に進み人類社会は飛躍的な発展を遂げ、今や人口は70億人を突破した。一方、環境問題、エネルギー問題、食料問題など複合的な負の遺産も背負うこととなった。1989年のベルリンの壁崩壊により始まった第5波では、世界がいっきにグローバル化しインターネットなどの情報通信と移動手段の急激な発展と人口増加により地球の相対的狭小化が爆発的に進行した結果、各地で紛争が絶えず生じ、多様性の爆発の兆候すらある。同時に、エイズウイルス、エボラ出血熱ウイルス、SARSウイルス (SARS-CoV-1)、新型インフルエンザウイルス、MERSウイルス(MERS-CoV)、そして鳥インフルエンザウイルスなど、新興感染症爆発の兆候が続いていた。そしてCOVID-19パンデミックが必然的に生じた。これらの新興感染症は環境問題として捉える必要がある。天然痘、結核、麻疹、マラリヤ、インフルエンザなどの感染症は、第2波に人類に伝播した。人類が農耕文明に入り野生動物を家畜やペット化するとともに定住化した。その結果として人口密度が上昇し、生活圏内に存在する蚊やネズミや家畜、あるいはペットなどから人類に伝播したものだ。すなわち、あくまでも人間社会の中で動物や昆虫などから伝播したものだ。しかるにSARSウイルス、新型コロナウイルスなどは人間社会とは一線を画す野生動物由来である。新型コロナウイルスがコウモリからどのような過程をへて人へ感染したかの詳細は現時点では不明であるが、人口増加と環境破壊などにより野生動物と家畜も含めた人類社会が限りなく接近し、野生動物から直接あるいは家畜などを介して人類に伝播したものと考えられる。これら新興感染症と区別するために結核や麻疹などは伝統的感染症と呼ぶのが相応しいと思う。伝統的感染症は1万年の歴史を経てほぼ定常状態にあるとともに、医学によりある程度制御可能な状況にある。しかしCOVID-19のような新興感染症は家畜ではなく野生動物からの人類社会への伝播であり、環境破壊と地球狭小化により今後頻回に発生することが容易に予想される。同時に、地球温暖化により、従来は熱帯地域の感染症であったマラリアやデング熱などの流行地域が拡大しつつある。このように、温暖化などの環境問題やそれと密接に関連するエネルギー問題、水や食料問題が人類社会に刻々と暗雲を投げかけている。実際異常気象がもたらす自然災害の激甚化が進んでいる。さらに、生命科学が一線を超えて、ゲノム編集/デザインベイビー、再生医学/生物学的寿命の破壊的寿命延伸、脳科学/心の操縦など、神の領域を侵しつつある。その一方ではサイバー空間と現実空間の融合が進み、情報が氾濫し、人々は情報に縛られ情報が社会を支配しようとしている。今人類は20万年の歴史上、第5波という大きなうねりの中にいることは間違いない。すなわちポストコロナは単なる通過点であり、人類は第5波が提示している大変動を如何にして乗り越えるかという長期的視野に立った観点が必要だと思う。
このように、第5波は環境問題、エネルギーや食料問題だけではなく、究極の次元にまで発展してきた生命科学や情報科学を、それらが内包する負の側面を乗り越えて、如何に社会に取り込んでいくかの問題でもある。環境破壊などの問題とも合わせて、これらの科学技術がもたらした負の側面を、地球市民としての自覚をもって科学技術により克服していかなければ人類の未来は開かれない。すなわち、SDGsをどのようにして達成するかの問題でもある。
新型コロナウイルスは「世界は1つである」こと、「国境はないこと」を人類に再認識させてくれた。今こそ「地球市民」としての自覚と、「相手の立場を尊重し、信頼し、助け合う、連帯と協調の精神」を胸に人類の未来を切り開かなければならない。
未来への啓示〜作成中〜