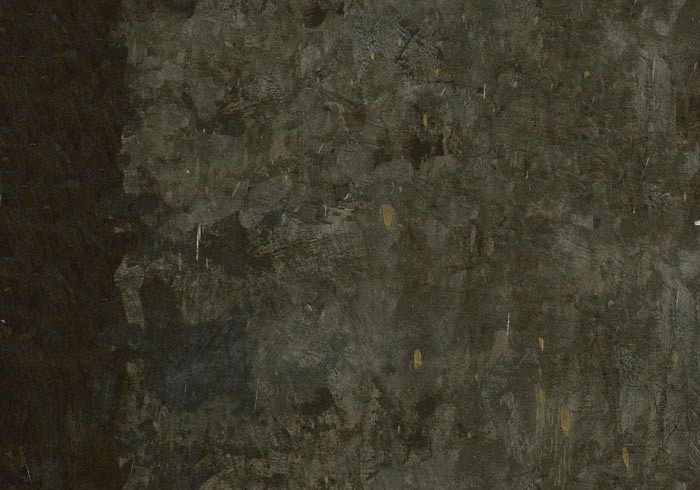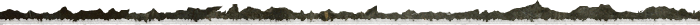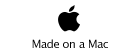ネットによる公開討論会”独創的研究とは”を開催して
2000年9月8日〜2000年12月24日
日本免疫学会ニュースレター8巻No2(通巻15号) でも書きましたが、私が高津先生からニュースレターの編集委員長を引き継ぎ早3年が過ぎ、このニュースレターから小安重夫編集委員長の新編集委員会にバトンタッチしました。この3年間,私たち編集委員が追い求めたことは20世紀の分子生物学の先頭に立ってリードしてきた免疫学が,21世紀を迎えて,さらに円熟味を増すとともに,21世紀においても輝ける学問であって欲しいという思いです.常に免疫学の進むべき道,あるいは独創的な研究は如何にあるべきかというテーマーを追い続けてきました(これらの記事は,日本免疫学会ニュースレターホームページ に掲載されています).ニュースレター8巻第2号(通巻15号) 掲載の吉村昭彦氏の“独創性とは何か、あるいは優れた仕事を成し遂げるには何が必要か” という記事がきっかけになり、ネット上で公開討論会“独走的研究とは”を開催しました(平成12年9月8日ー12月31日) 。時同じくして白川英樹博士のノーベル化学賞受賞を機に、我が国発の独創的研究がなぜ少ないのか、日本には独創的研究がでにくい研究環境があるのか?が新聞紙上で話題を集めました。さらにアメリカのISI社が過去18年間(1981-1998)にHigh-Impact Paperを少なくとも12編発表した日本人研究者30人を発表しました(ISI Honors Most Highly-Cited Authors in Japan) 。分野別の内訳は生命科学18人、材料系7人、化学系1人、天文学2人、環境化学2人でした。これらの話題は日本における独創的研究、創造的研究環境の是非を巡り様々の議論を呼び起こし、初等教育、大学や大学院における教育のあり方、さらには日本の研究システムにおけるさまざまな問題点にまで議論の輪が広がったのは皆さま御存知のとうりです。今回小安編集委員長から公開討論会の紹介をするようにとの依頼を受けました。本公開討論会はウエブサイトに引き続き公開中ですので、内容はウエブサイトをご覧戴ければ幸いです5。ここでは討論会の紹介と私の率直な感想を述べるにとどめたいと思います。
ことのおこりは、15号の編集作業が完成し、後は印刷所に原稿を送付するだけになっていた8月末の本庶先生からの私への1本の電話に始まります。“JSI Newsletter15号、吉村昭彦氏の“独創性とは何か、あるいは優れた仕事を成し遂げるには何が必要か”4というエッセイを読み、少なからぬ違和感を覚えたので、あえてJSI Newsletterに意見を投稿したい“という主旨であったと思います。すでに15号の編集は終了しており、さりとて本庶先生の原稿を16号に掲載するのでは泡の抜けたビールの様なものなので、編集委員会で相談の末、ネットによる公開討論会”独創的研究とは“を開催することにしました。幸いにもこの討論会には石坂公成先生をはじめ13人のかたから合計16件のコメントが寄せられ大変盛り上がるとともに、この問題に対する関心の強さが改めて浮き彫りになりました。また討論を通じて研究を介してのみ付き合っている同輩の研究者や、大先輩の先生方の人となりや考え方がじかに伝わってくるというまたとない機会であったと感じたのは私だけだったでしょうか?
<そもそも研究とは、好奇心からスタートするものである。“なんだろう?” “不思議だな?”という自らの問を心行くまで追求することが、研究者の楽しみではなかろうか。--------「流行を追う」ということは、自らの中に何かを知りたいという好奇心が希薄であるせいではないのであろうか>という9月8日投稿の本庶先生の、1〕独創的研究とは何か にはじまり 12月24日の淀井氏の、16)独創性についての独言 、 までの4ヶ月間のあいだに、公開討論会は以下のような展開をみせました。
1〕本庶 佑、「独創的研究とは何か」(2000/09/08)
2〕吉村 昭彦、独創的な研究とは何か(2000/09/11)
3) 平野俊夫、生命科学に真の意味の創造的研究は存在しうるか?(2000/09/11)
4〕高浜洋介、何のための「独創性」か?(2000/09/14)
6)平野俊夫、独創性を育む研究環境の整備が急がれる、(2000/09/19)
9)黒崎 知博、研究とは自分をかけた壮大なゲームである(2000/09/27)
10〕市原 明、何故日本には独創的研究が育ち難いか?(2000/09/27)
11〕平野俊夫、雑感---日本の研究は世界にいかほどのインパクトを与えたか?(2000/10/07)
12〕石坂公成、独創的研究をするために必要なこと(2000/10/23)
14)深田俊幸、「“独創的研究とは何か”を語る前に」、(2000/11/02)
15〕平野俊夫、司会としてのコメント(2000/11/02)
16)淀井淳司、独創性についての独言、(2000/12/24)
この間、当然のことながら、独創的研究とは何か?あるいは独創的研究を行うためにはいかにすべきか?に討論は集中しましたが、見逃してはならないのは、この公開討論会を介して、新たな問題、すなわち、市原先生の、何故日本には独創的研究が育ち難いかという問いに始まり、では独創的な研究をするための研究環境は如何にあるべきか? 独創的研究をどのように評価するのか?しいては現在の研究の評価システムは適正なものなのか?研究費の配分システムはこれで妥当なものなのか?などが浮上しました。そして石坂先生の、<----今回の公開討論会の目的は、恐らく“日本から独創的な研究を輩出させたいが、そのためにはどうすればよいのか?”を考えようということだと思う。----“学問的常識に合わない実験事実を見逃さないこと、----周囲の反対に会いながら、自分の仮説を証明し、他の研究者がその結果を役に立ててくれて始めて学問的貢献と言えるのではないだろうか?------独創的な研究を奨励するためには、科学研究費の制度を大改革することが必要だと思います----。>となる。
これらの討論の中に数々の注目すべき言葉がありました。例えば、<オンリーワンになることが独創性への最も近道であると考える(本庶)>、<私は”努力は無限”という言葉が好きです(吉村)>、<もしかしたら21世紀の免疫学は難解な数学に変貌しているかもしれないと思うのは私だけでしょうか?〔吉村〕>、<生命科学における独創性とは研究のプロセスにある-----なかでも“祈る”という言葉に生命科学研究の真髄がある〔平野〕>、<「研究はバクハツだ」!〔高浜〕>、<研究費の問題は、「独創性を育てるには何をすべきか」という、これまた繰り返される問題と密接に関係する〔小安〕>、<激しく競合する科学者の姿を想像し, あえてWatsonの要望する科学者のモラルについて提言する次第である(山岸)>、<研究とは自分をかけた壮大なゲームである〔黒崎〕>、<下からの改革は困難である。制度を変えるのは時間がかかる、だから指導者が全ての点で努力すべきである〔市原〕>、<現状では翌年の研究費も保証されない私たち普通の研究者はどうしたらよいのだろうか(北村)>、<真の独創性を忌避する日本の風土はそれ自体が研究対象になるべきことの様にも思われる(淀井)>、<仲間内のうわさ話やブランド名で評価するような村社会的方法でなく、真に個性のある仕事をポジティブに評価する何らかのシステムが必要であろう〔淀井〕>、等々、他にも数えきれないくらいありました。詳細は公開討論会のウエブサイトを見ていただきたいと思います。
ヒトゲノム計画もほぼ終了した今日、また種々のテクノロジーが急速に発展した今日、果たして、今までの生命科学の発展の原動力になってきた従来の研究手法が、あるいは研究に対する我々の発想が、今後も引き続き生命科学の次元を越えた発展に寄与しうるかという素朴な疑問が目の前に立ちふさがっています。一方では、これまでに蓄積された膨大な免疫システムにおける研究成果をもとに、この複雑で、巧妙に行われている免疫反応をシステムとして理解し、それを実際の医療の現場にいかにして、還元するかという非常に魅力的なテーマーに対峙しています。私が28年前に免疫学を志したときは“夢のまた夢”であったことが、いまや現実問題として私たちの目の前にあらゆる可能性を秘めて開けているように思います。いま世の中は政治や、経済、そして大学システムや科学研究を取り巻く環境が激しく変化する、その夜明け前を迎えている感すらあり、そこには期待と、不安と、もどかしさ、そしてそれらの入り交じった閉塞感が漂っている感もあります。21世紀の更なる生命科学の発展のため、今一度“独創的研究とは”という問い掛けを自らに自問自答することにより、次の新たな次元の展開のために何らかの起爆剤になればと考えています。
ただ忘れてはならないのは、”独創的かどうかという判断“ は社会的評価を内包しており、研究者と社会が対峙する過程で必然的に発生してきた概念であるということです。学問 というのは、昔は趣味であり、宮廷や金持ちのパトロンの庇護のもとに行われていたが、現在の研究環境では公的な研究費の助成を受けており、社会的な資金に頼って研究をやっている以上、評価をどうするかが、国のレベルで、将来を論じるときに大変重要な要素になります。 ”独創的な研究とは”を考えている過程で、 ”個人の知的好奇心などのモチベーション”の問題と対峙するかたちで、職業人としての研究者のあり方と、研究費の配分や評価方法の問題をいかに適切なものにするかが、これからの日本の基礎研究を発展させていくためには大変重要な意味を秘めています。「独創性とは何か」、「独創性をいかに評価するか」という非常に重要で且つ困難な問題から「独創性を育てるには何をすべきか」という問題へと波及していくことになります。これらの問題は引き続き小安編集委員長を中心とする編集委員の方々に託され、再度ニュースレターや公開討論会で問題にされることと思います。
今回の公開討論会が日本の免疫学の更なる発展に少しでも寄与できることを祈るとともに、今回公開討論会を開催するにあたり、御尽力いただいた旧編集委員の方々に再度御礼申し上げます。また本公開討論会に積極的に御参加いただいた方々にこの場をお借りして深謝致したいと思います。