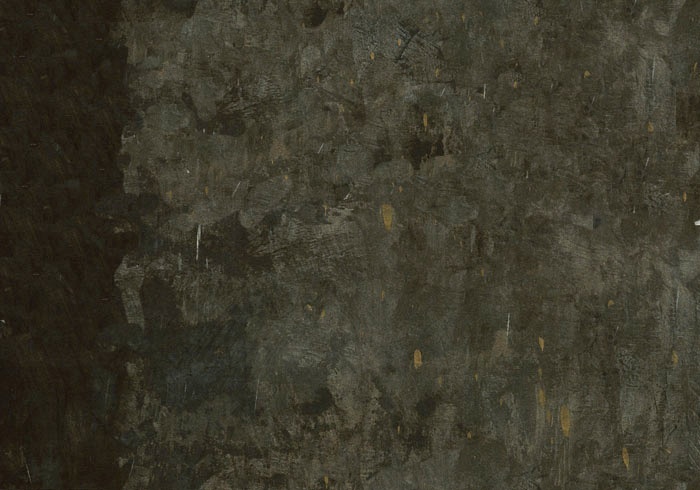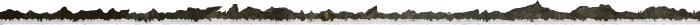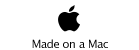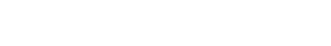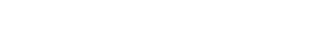胡蝶の夢
昔荘周夢に胡蝶となる。栩栩然として胡蝶なり。自ら愉みて志に適えるかな。周たるを知らざるなり。俄然として覚むればすなわちきょきょ然として周なり。知らず、周の夢に胡蝶となるか、胡蝶の夢に周となるかを。周と胡蝶とは、必ず分あらん。これをこれ物化と謂う。―――「荘子」、岸田陽子訳、徳間文庫より。
「胡蝶の夢」はなかなか味わい深いものがある。単に相対的なものの見方だけではなく、夢の胡蝶が今の自分を夢見ているのか、それとも今の自分が夢で蝶になっているのか?このような相対的な物の見方が問題ではなく、そのようなことはどうでもいいと荘子は言う。どちらにしてもあるがままの今を楽しむことが全てである。この考え方からは、過去と未来、そしてそれを仲介する今の瞬間、この瞬間が全てであると言っているように、私には思われる。
最近、私が大学生のころに読んだ「荘子」中公新書、福永光司著を開いてみたところ、本の至る所に書き込みが観られる。最後の書き込みの日付けは1969年3月19日(当時22歳で大学4年生)となっている。むきになって荘子に反論しているところが青臭く、また当時が懐かしくもある。今回改めて福永氏の古びた本を読み直したが、なかなか素晴らしい著書だと思う。改めて「不知の知」の意味を噛み締めた。善と悪、正義と不正義、美と醜、などなど、物事の対立はもちろん見方を変えれば全く反対になる、しかしこのような判断はあくまでも「知」のなす技であり、人間が「知」を捨てられない限り「知」の限界を超えられない。「知」の所産である価値判断によって人間の自由なあり方を束縛し歪曲する。「知」を超える、「知」から分つ事、乃ち、あるがままを、あるがままに受容すること。これが「不知の知」と説かれている。
私は相対的な物の見方が好きだ。その考え方が私の人生の基本です。ただ社会に対する表現系は、荘子とはかなり異なるように見える人生を送って来たかもしれない。事実40年間、知的好奇心に駆られて研究に打ち込んできたが、2007年に肺ガンの手術を受けてからの直近の5年間は医学部長を3年間務め、現在は大阪大学総長を努めている。そして、あるがままの姿を受け入れるのではなく、なんとか現状を変えよう(自分の価値判断で良くしよう)と毎日奮闘している。この姿は荘子のそれとはほど遠い境地を彷徨っているとも見える。
生を善しとし、死を善しとする。一切万物は自生自化する。人生は常なきものである。「人間は一瞬一瞬に断絶の深淵の上をふまえながらその断絶を一つの連続として自己の一生を生きて行く」―――福永光司著荘子より。絶えず死の前にたたされている「現在を現在として精一杯に生きる」、「この瞬間を必死に生きる」と荘子が言っているようにも聞こえる。私は常日ごろ、学生に「目の前の山を登りきる」ことが重要と言ってきた。目の前の山を登りきることにより未知の可能性が、未来が開ける。その頂への最後の道のりこそが最も過酷なときであり、この試練を乗りきった瞬間に目のまえの展望が果てしなく広がると、いつも若い人に、あるいは自分自身に言い聞かせて来た。この言葉がある意味では荘子の世界とはかけ離れているように思えるかもしれない。しかし、見方をかえれば「今の瞬間に全てが凝縮している」というある意味で刹那的、その刹那に全力を注ぐ、そのことにより、迷い、不安、葛藤、など様々な心を一点に集中させることによりその瞬間を生きる事に通じる。荘子の考え方は見方によれば達観して世の中を見下ろす観もあるが、達観しながらも、その瞬間を生き抜くという意味では私の考え方と通じるものもある。荘子の考え方では、このような問いかけそのものも、そもそもどうでも良く(結論/決めつけ、価値観の判断など)、あくまでもあるがままを楽しむ、あるがままを生きる、という事だと思う。ある意味では私も荘子と同じ線路の上を歩いているのではないかと思う。社会に対する表現系が他人からみれば荘子と私では大変ことなるように見えるかもしれないが。
それにしても大鵬高く飛翔する下りは壮観だ。これほど大きな世界はあるだろうか?感激で、心が震える。
北冥に魚あり、その名を鯤となす。鯤の大きさ、その幾千里なるを知らざるなり。化して鳥となる、その名を鵬となす。――――「鵬の南冥に徒るや、水の撃すること三千里、扶揺に搏きて上がること九万里、去りて六月をもって息こうものなり」―――小知は大知に及ばず、小年は大年に及ばず。なにをもってその然るを知るや。―――岸陽子訳荘子より。大鵬は3千里の海面を波立て9万里の高さに舞い上がり、一路南冥を目指す。
蝉や小鳩になにがわかる。小さな世界に住む者には想像もつかない大きな世界がある。時間も同じ。朝菌は1日という時間がわからない。蝉は1年という時間が理解できない。人間は千年という時間の意味が果たしてわかるだろうか?まして137億年という時間をや。
クリストファー・ロイド著の「137億年の物語」(野中香方子訳、文藝春秋社)は、再度、物事を達観するという意味で大変刺激をうけた。宇宙誕生から137億年、地球誕生から46億年、そして生命誕生から40億年である。人類は20万年の歴史の中で、何を学び、そしてどちらに向かって進んで行こうとしているのか?荘子から宇宙の話へ、そして未来へ、新年のはじめにあたり人生を考える時が静かに流れて行く。